月刊TIMES×鈴木邦男
2016年1月29日 11:27:53
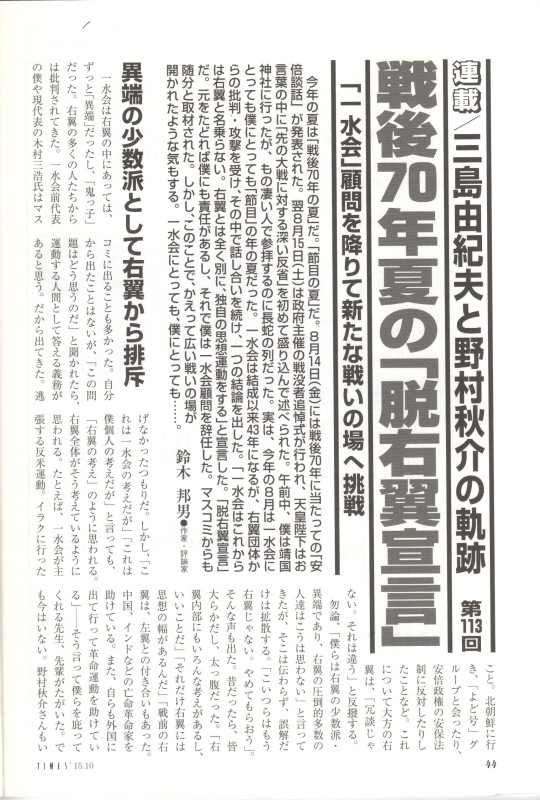




鈴木邦男さんとの出会い
初めて鈴木さんにお会いしたのは、多分もう20年くらい前だ。大塚の居酒屋だった。ぼくは音響としてその舞台についていた。その日の公演を終え、お客さんと飲みに行っていたのだ。鈴木さんは、お客さんとしてその公演を見に来ていた。
ぼくは、片隅で役者さんと話していた。その席に鈴木邦男さんがいらっしゃることは、もちろんわかっていた。以前から鈴木さんの著作をわくわくしながら読んでいたし、いろいろな事件にも興味があった。
その時、演出家がぼくを呼んだ。演出家の前の席に鈴木さんがいた。
「高木ちゃん、高木ちゃん、ほら! 右翼!」
と、その演出家は鈴木さんを指さした。
「高木ちゃんも右翼じゃん。ほら、本物の右翼!」
と、真面目な顔をして鈴木さんをさしている。
そんな紹介にぼくはどうしたらいいのかわからず、とにかくきちんと挨拶をした、と、思う。よくは覚えていない。鈴木さんが、にこにこ笑っていたことだけは覚えている。多分、鈴木さんの著作を読んでいること、三島由紀夫のことを始め、山口二矢や二・二六事件などに興味があるという話をした、と、思う。思う、というのは、思い出せないからだ。当時、鈴木さんを前に話せることといったら、そのくらいしかなかったはずだ。数分の邂逅だった。
読書と見沢知廉と鈴木邦男さん
その後もぼくは音響家や作曲家としてあちこちの舞台につき、また脚本家として作品を発表したりしていた。鈴木さんとはまったく関係のないところで。
そして、2005年。見沢さんが亡くなった。
見沢さんの小説を舞台化したいと思った。すぐにでも作品を創りたかった。けれども周囲の状況がなかなかそれを許してくれなかった。一年経った。2006年。見沢さんの三回忌に作品を発表しようと決めた。
決めたはいいが、
さて、どこから手をつけたらいいものかと思案していた。下手な動きをしたらこの企画は実現しないだろう、という予感があった。何故と言って、いかんせん扱う人物が有名だったし、思想エリアが偏り過ぎていたからだ。見沢知廉という大事件を起こした人物。独特の小説。右翼や左翼という膨大な数の関係者。彼の死に対する不穏な噂。同じ陣営ながら見沢さんに対する評価もわかれていたし、ぼくの知らないエリアでの複雑な関係性も見え隠れしていた。
ぼちぼちと動き始めようとしていた時、偶然、(それは本当に偶然だった)鈴木さんに再会したのだ。
阿佐ヶ谷の劇場。ぼくは観客としてその舞台を観に行っていた。慣れ親しんだ劇場だった。客席に入り、後ろの方に腰を下ろした。人気の劇団だった。たくさんのお客さんが入場してきた。
ぼくの隣に、なにかぶつぶつ言いながら一人のおっさんが腰をかけた。若い女の子を連れている。ぶつぶつ言っているのは、その女性に言っているのか、独り言なのか判断できない。ぼくは、読んでいた本から顔をあげた。
鈴木邦男さんだった。
天の配剤! そう思った。ぼくはすぐに声をかけた。
こうこうこうで、こうでこうで、見沢さんの舞台を上演したいのだが、相談にのっていただけないだろうか、と。
鈴木さんは、「へー、すごいねー、ぜひやってください。かあちゃんもよろこびますよ、ねー」とあまり興味もなさそうに言われた。多分、そんな似たような話をあちこちで聞きすぎていたのだろう。そして、隣の女性に「高橋さん、一水会に一緒にいったらいいじゃないか、そうだよ、そうしなよ」と、ぼくのことを、隣の高橋さんという女性に丸投げしてしまった。
その瞬間が、始まりだった。
高橋さんは、ぼくを一水会に、(当時のぼくにしてみれば、『あの一水会に?!』という感じだ)連れて行ってくれた。ゼミに参加し、一水会活動の片隅に身を置かせていただいたりした。木村三浩代表にも上演に関して骨を折っていただいた。
そうして始まった「劇団再生」
鈴木邦男さんとの出会いがなければ、こうして今、ぼくは、ここにはいなかっただろう。思い返しても不思議なものだな、と思う。そして、鈴木さんとの出会いは、作品だけではなく、ぼくの読書体験も変えていったのだ。
2006年の一水会の忘年会。
どんな巡りあわせか、席が鈴木さんの隣だった。その席で突然、(ほんとうに何の脈絡もなく)鈴木さんが、聞いてきたのだ。(その脈絡のなさ、鈴木さんの突然性は、何年も経ってようやく慣れたものだが・・・)
「高木さんは、吉村昭読みましたか?」
鈴木さんのそんな問いにぼくは、答えた。「文庫で出ているのは、多分全部読んでます」と。
「おー、凄いねー。じゃあ、何が良かった?」と、鈴木さん。ぼくは、『破獄』や『プリズンの満月』、『仮釈放』、『大本営が震えた日』といった作品を挙げた。
「やっぱり『破獄』だよね」と鈴木さんは言われた。
そして、2007年、劇団再生は、見沢知廉原作の『天皇ごっこ』を上演した。
その後の作品において鈴木さんは必ずプレトークに来てくれる。ありがたいことだ。そう言えば、最初はアフタートークだったんだ。上演後に鈴木さんと話をしたんだった。阿佐ヶ谷ロフトだ。上演後のアフタートーク。でも、演劇のお客さんはそんなトークにはあまり興味がない人も多く、上演後多くのお客さんが席を立って帰ってしまった。鈴木さんをお呼びしながら寂しい観客席だった。申し訳ないな、と思っていたら、鈴木さんが、
「いい話をするんだから、みんなに強制的に聞かせたらいいんですよ! 芝居が始まる前にやったらいいじゃないか」と言った。
で、次から、そうした。プレトークになった。多分もう20回以上もそんなことを続けている。毎回鈴木さんは駆けつけてくれる。今では、鈴木さんとのプレトークの回は大人気の回となった。今回の作品でも、プレトークの回は早々に売り切れてしまうだろう。
10年。密とも粗とも言えない鈴木さんとの関係。その距離感が劇団再生を育て、ぼくの読書を育ててくれた。ふと、そんなことを思い出したりすることもある。

