『キルケゴール』【人類の知的遺産48】
2016年3月16日 01:04:55
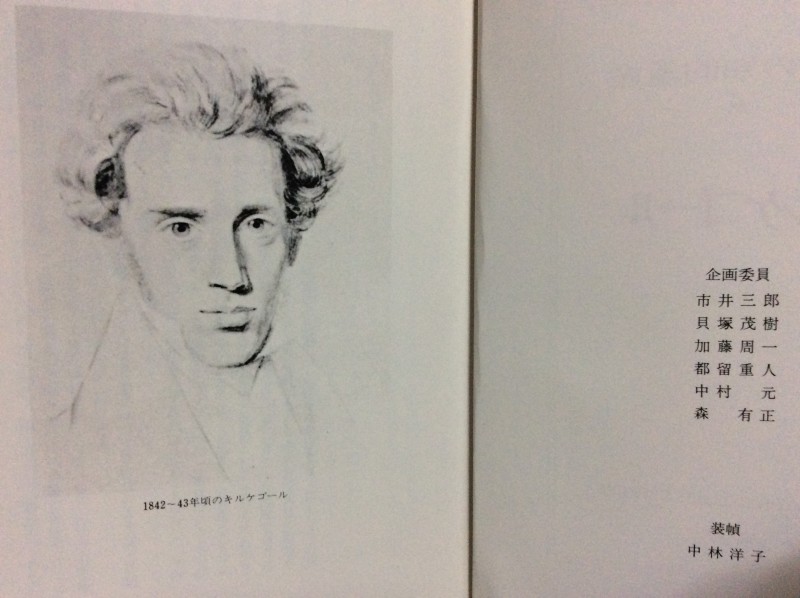
こんな現代だからこそ、キルケゴール
ようやくキルケゴールを読む時代になったのかもしれない。そう思う。
他国の流行は知らないが、日本では何故か、思いついたようにある哲学者が取り上げられ、流行というまな板の上にのせられる。そんな時、一体誰がそれを仕掛けているのかと、いつも不思議に思うのだ。
ハイデガーしかり、ヘーゲルしかり、ニーチェしかり、マルクスしかり。
そして、その流行の期間は、書店に解説書や関連書籍がこれでもかと平積みされ、売れていく。でも何故かそこに原典は並んでいない。言葉が意訳され、都合良く切り取られ、時代の型にはめられ売れていく。
そうやってたくさんの本が売れながら、もう何十年も何かが変わったとは思わない。前節の、何か、には、もちろん、あなた、が、含まれる。そして、前節の、あなた、には、もちろん、百万人のとい修飾がされている。ついこないだまで、ニーチェニーチェと言ってたではないか。ヘーゲリアンだの、マキャベリズムだの、プラグマティックだと言っていたではないか。笑止。
それだけの本が並び読まれ、その結果を想像するに人は、少なくとも大人は、どんどん、良く、かっこ良く、なっていっているはずではないか。それがどうだ。かっこいい大人は減っている気がする。それが、ぼくの周りだけに限定された現象だとしたら、ぼく自身に問題があるのだろ。そうかもしれない。それならそれで仕方がない。その限定を解除しよう! と意気込んでこれまでの方法をまるっきり反対側にシフトできるような器用さは持っていないような気がする。器用は器用で器用貧乏と言われるが、どうもその器用さとは、別物だと思われる。とするならば、僕の周りから今後もこれまで同様の比例において、かっこいい大人が少なくなっていくのかもしれない。
そして、今のこのまま僕は、人との関係が減っていき希薄になり、単純化されるのだろう。五年前、ぼくのアドレス帳には、800件を超える登録があった。今は、200件を下回る。それでも手が回らないのだ。
ということで、こんな、そんな時代だからこそ、キルケゴール。
僕自身の論点を一般化するつもりはないが
前段の文脈を使った方が、こんな時代、っていうのを説明しやすいかな、と思っている。
論点は簡単だ。
「私という実存」と「こんな時代」
こんな時代、というのはまさに現代の有り様だ。情報化社会という言い方でもいいし、ネットワークの時代でもいい。関係優位でもいいし、共同体の仮想化でもいいだろう。以上の四つの言い方で充分に「こんな」を体感できる時代。情報とは何かということがはるか後方に置き去られ、もはや数えることが絶対に不可能なほどのテキストやメディアが、情報、とされ、僕たちの、個人の安全圏を楽々と突破し、あの真夏の満員電車のような不快感と嫌悪感を24時間感じなければならない。
少なくとも、僕はそうだ。だが、しかし、そんな情報というあり方を歓迎している人が多いこともわかっている。満員電車、半袖から伸びる腕にかいた汗、その他人の汗がべっとりと自分の腕や耳に塗りつけられる不快と嫌悪と恐怖。そんな、僕には耐え難い状況を好み、わざわざ満員電車に乗り込むものもいる。目をぎらつかせ満員電車の中で異性の間近に近づこうとする者。なるほど、「こんな」時代の情報とそっくりそのままじゃないか。
情報、そしてネットワーク。性欲異常者以上に増殖する情報異常者。困ったことに性欲異常は本人が嫌という程自覚するのに対して、情報異常者は、無自覚であるだけならまだしも、嬉々ととしてその正当性を主張する。その主張があまりにも整然と感じられるので本人も周囲も異常性に気がつかない。いや、今は、その異常性を保つことが正常であるのだ。という、「こんな」時代。関係優位も共同体の仮想化もわかるだろう。
さて、僕が僕として生きるのに、前述の発展的関係は必要がない、なかった。と、断言する。もちろん、自分の存在確認を必ず他者に委ねている、という存在論が今のテーブルではない。存在論においては僕は必ず関係という形而上的枠内にしかいることはできない。そうではなくて、今ここでのテーブルは、実存だ。人が人として生きるのに情報とは何か、関係とは 何か。
僕にとって情報は、僕の価値判断を決めてくれるものではなかった。僕の態度決定を教えてくれるものではなかった。
ということだ。
サンプルが、僕の数十年では少ないというなら、人は、一体何によって価値を判断し、態度を決定するのか、教えて欲しい。このまま情報やネットワークは加速的に増殖し、生活に欠くべからざるものとなっていく。しかし、そこには省みられることのない主体が、必死に叫び声をあげるだろう。
主体的自覚
そう呼ばれるものだ。少なくとも 僕のそれは今、叫ぶこともできないほどの酸欠の中にある。
キルケゴールは、生涯をかけて、人間の、思想の、主体性の問題を問い続けた。
最後にキルケゴールのこんな言葉
眼で読んだだけでなく、全身を打ち込んで
-心窩(みぞおち)で-
読んだ
キルケゴールが、ある本について語った言葉だ。
キルケゴール自身、自身の著書をそんな風に読んで欲しかったのかもしれない

